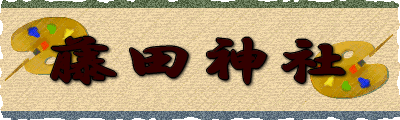
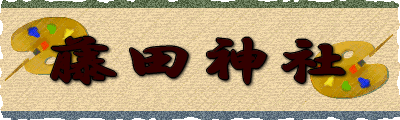
 藤田神社
藤田神社
 配田神社
配田神社
藤田神社
1.祭神:大年神
2.由緒:初め八反田区の西端市川の付近に鎮座せられてあったが、延宝四年(西暦1676年)大洪水節現今境内の北面岳下迄流れ着いた。依て両部落協議の上今の處に社殿を建て奉遷したと伝えている。明治7年2月村社に列し、同26年拝殿を改造し、同43年本殿を改築、大正3年祝詞舎を新築した。
3.神社明細帳:殿改造明治26年2月24日、社殿改築同43年10月2日、祝詞舎新築大正3年3月11日
4.境内:1064坪 官有地
5.営造物:本殿:銅瓦入母屋造 1坪、祝詞舎:瓦葺入母屋造 5坪、拝殿:瓦葺入母屋造 8坪
6.祭日:夏祭り:7月18日、 例祭:10月17日
7.崇敬者:95戸、長目区八反田区両部落が祭祈せるもの。
<<神崎郡史より>>
ご参考:延宝8年(1680年)、徳川綱吉五代将軍に就任
配田神社
1.由緒:従来薬師院境内にあったのを明治10年乙第四號達に基づき藤田神社境内に移轉合併した。
2.祭神:菅原大神
<<神崎郡史より>>
 藤田神社:本殿
藤田神社:本殿
 藤田神社:山門
藤田神社:山門
 |
百度石 |
 |
藤田神社(祝詞舎) 曾我兄弟仇討図の絵馬 (現在は風化して見えなくなっている) |
 |
吽像 狛犬は獅子ともいわれ、中国漢代以降の帝陵前に置いた石獅子の系統を引くもので、守護神的な性格をもっている。わが国に狛犬が出現したのは平安時代からのようで、製作年代が示されている石造狛犬の最古の最古のものは、福岡県宗像神社の建仁元年(1201年)のもの、播磨では明石の柿本神社の宝暦4年(1754年)のものが最も古い。 口を開く阿像(アゾウ)と口を閉じる吽像(ウンゾウ)とで一対にするのが一般的で左に吽像が置かれている。いずれ雌、雄ときめがたいのが特徴である。 |
 |
阿像 旧狛犬が老朽化し崩壊の危険がある為、平成16年10月、長目と八反田で更新した。 |